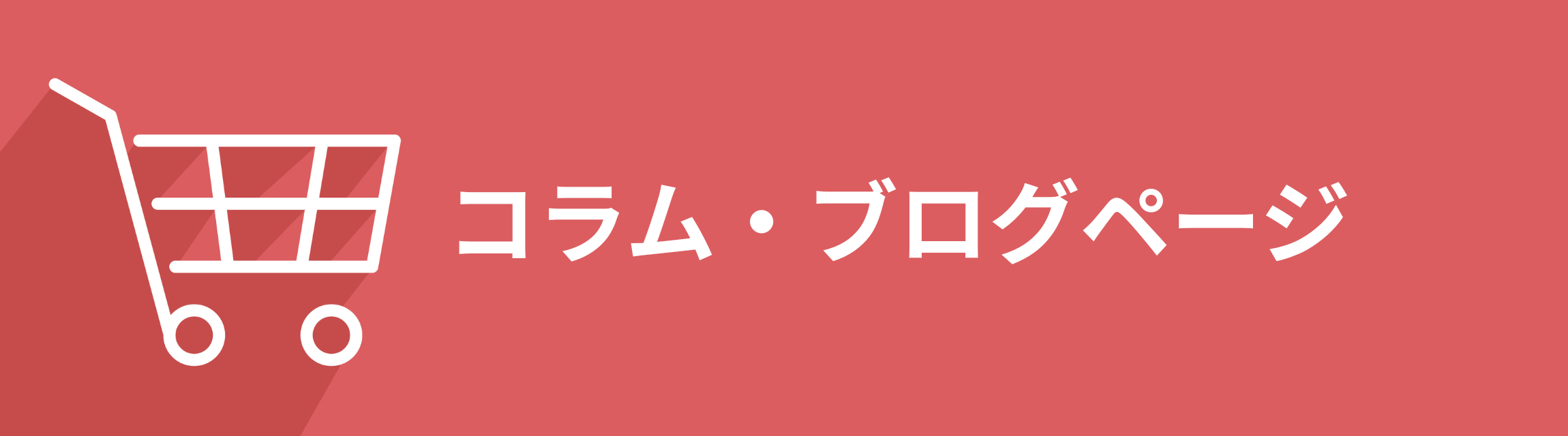
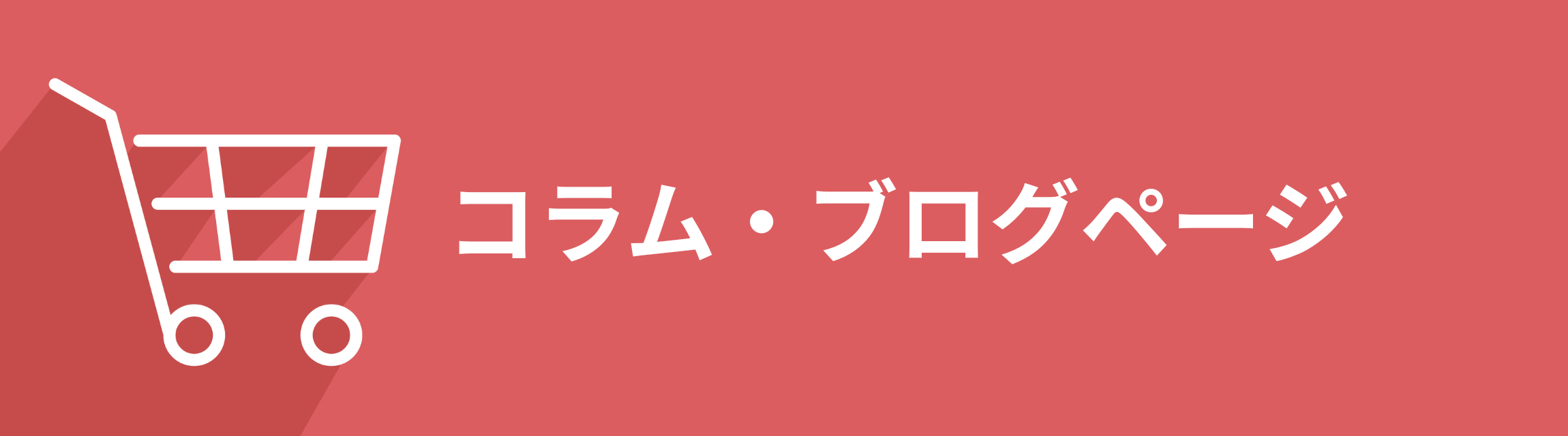
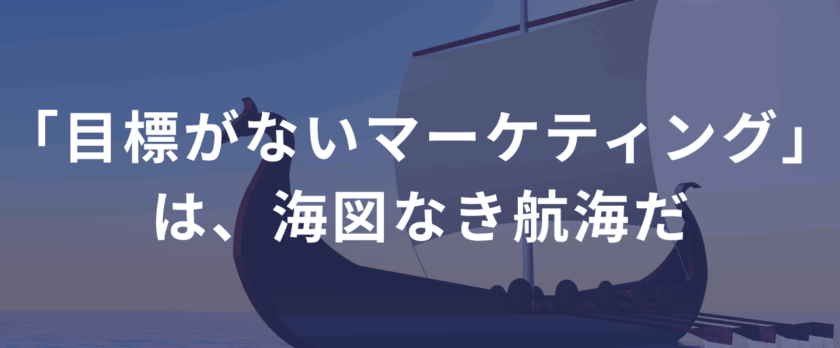
「いま何を目指してるんですか?」
この問いに答えられない現場は、想像以上に多い。そして、目標がないということは、意思決定の軸がないということでもある。
そんな「船頭のいない船」は、いつしか漂流する。
実務を回している側の声:
「上から売上上げろって言われても、何をどこまでやればいいかわからない」「正直、毎月の目標が“なんとなく”なんです」
一方、経営者の本音:
「現場に任せてるが、数字の妥当性が見えない」「評価をどうつけたらいいかも曖昧になる」
これは感覚ではなく、「構造の問題」だ。
目標とは、努力と資源の向かう先。マーケティングにおいて目標が存在しないというのは、「ゲームのルールなしに点を取りに行く」ようなものだ。
目標がない現場では、以下のような“病”が蔓延する:
つまり、「マーケティング=仕組み」にならない。
これはECでも同じだ。広告を回す、LPを改善する、CRMを打つ――。これらを“点”でしか見れない組織は、長期的に再現性ある成長はしない。
目標とは、「行動を定義するフレーム」である。
▶ ポイントはこの3つ:
マーケティングの目標設定は、単に数字を置けばいいわけではない。「売上」という結果に対し、“どのレバーで動かすのか”を整理する。
売上は分解できる:
売上 = セッション数 × CVR × 客単価 × 購入回数
ここで重要なのは、すべてに手を出さないこと。どの要素を重点的に改善するか、「一本主軸を決める」のが目標設定の本質だ。
例:
KGI(目的):
売上1.2億円(前年比+20%)
CSF(成功の鍵):
CVR改善をメインレバーに設定
KPI(行動指標):
CVR 0.6% → 0.9%(3ヶ月で)
このKPIの根拠となるのは、「あといくつ売れれば目標に届くのか?」という数字の逆算である。
| 要素 | 意味 | チェックポイント |
|---|---|---|
| S(Specific) | 具体的か? | 誰にでも伝わるか? |
| M(Measurable) | 計測可能か? | 数字で追えるか? |
| A(Achievable) | 実現可能か? | 現実的か? |
| R(Relevant) | 方針と一貫してるか? | 経営や事業目標に沿っているか? |
| T(Time-bound) | 期限があるか? | いつまで? |
つまり、目標とは組織内の“共通言語”なのだ。
目標を語ることは、未来を語ることだ。
「この数字を達成したい」と言うとき、それは「この未来を実現したい」と宣言しているのと同じである。
数字は、“成長のシナリオ”を言語化したもの。そして、組織における共通のコンパスである。
ManyCの視点
ManyCでは、売上を上げるための構造だけでなく、「数字に宿る意味」まで含めて設計し、実行支援を行っています。
単に施策を打つのではなく、数字のストーリーを描き切ること。それが、目標設計の真価です。